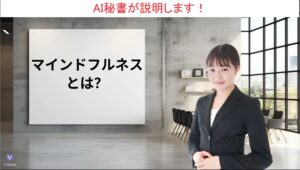コンビニで売っている水はなぜ500ミリリットルより2リットルのほうが安いのか
今回は、コンビニで売っている水はなぜ500ミリリットルより2リットルのほうが安いのかについて説明します。
500ミリリットルの水は個人で気軽に購入する傾向があり、価格に対する感度が低いため、高めの価格設定と、高い利益率の設定が可能です。
一方、2リットルの水は家庭用として定期的に購入されるため、価格競争が激しく、価格が抑えられやすく、低い利益率の設定となりがちです。
500mlのほうが、利益率が高く、高めの価格設定が可能なのに、どうしてコンビニは低価格で利益率の低い2リットルの水も販売しているのでしょうか。
それはズバリ、スーパーから顧客を奪うための戦略です。
共稼ぎで、仕事が忙しくて、日用品が安いスーパーの空いている時間帯に買い物に行けない方や、スーパーまでは遠いけれど、近くにコンビニはあるという方などは、日曜品がコンビニで買えたらいいのに、と思うのではないでしょうか。
日用品がスーパーと同じ値段で売っていれば、急いで買い物に行かなくても、遠くまで買いに行かなくてもよくなり、スーパーに行かず、日用品をコンビニで買うようになります。
日用品をコンビニに買いに行くようになると、ついついほかの商品にも目が行き、ついで買いをしてしまいます。
低価格で利益率の低い日用品を置いておくことで、集客力を高め、高価格で利益率の高い商品を買ってもらうのです。
このように、コンビニでは、500ミリリットルと2リットルの水のように商品を組み合わせて販売することで、集客力を高め、全体の収益を上げ、利益率を最適化しています。
ほかに同じような戦略をとっている業界があります。
そう、ドラッグストアです。
ドラッグストアの利益の根幹となっているのは、高い粗利率を誇る医薬品と化粧品です。
しかしいずれも回転率が悪く、集客しやすいものでもありません。
そこでドラッグストア各社は、洗剤やティッシュペーパーといった普段使いの日用品や食品類を充実させ、なおかつ特売品を店頭に置くことでお客さんを呼び込み、医薬品や化粧品の購買へつなげるという戦略をとっています。
これが昨今の、ドラッグストアのスーパー化の要因となっています。
この記事の内容は、YouTube動画でも配信しています。